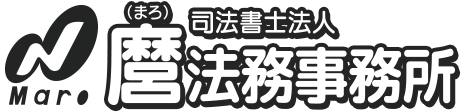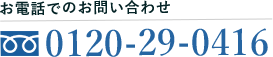相続・遺言
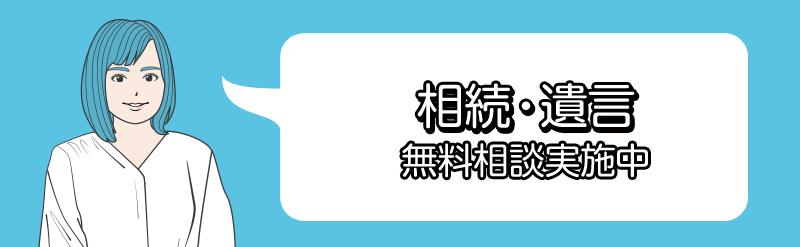
- 父が財産の全てを兄に譲ると遺言を、弟の私はもらえないのでしょうか??
- お金だけを残して父が他界、どうしたらいいのでしょうか?
- 父の財産を兄が独り占めに、どうしたらいいのでしょうか?
- 胎児にも相続の権利はあるのでしょうか?
- 遺言を残したいのですが、何か決まりがあるのでしょうか?
相続
亡くなった人の財産を遺産といい、一定の家族が引き継ぐことを相続といいます。 悲しみに暮れている時に多くの手続きを行わなければなりません。また、遺産を相続するのは大変な作業です。 遺産相続は、その査定や課税方法が複雑であり、素人が理解するには骨の折れる作業です。 相続の開始は被相続人(相続されるひと)の死亡や失踪宣告により開始します。相続税の基礎控除額
相続税は、相続が起きると必ず払わなければならないものではありません。 相続税は遺産相続の総額が一定額を超える人のみ支払えばいいということを知っておきましょう。 その金額はいくらかといいますと3000万円と法定相続人の人数に600万円を掛けて求めた金額とを合計した金額です。 この金額を遺産に係る基礎控除額といいます。 例えば、相続財産が1億円で相続人が3人の場合の基礎控除額は4800万円になります。 相続税を申告する必要のある人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人(死亡した人)の住所地の所轄税務署に申告する必要があります。必ず自分で申告書を取りに行かなければならないので注意しましょう。 相続税を申告しなければいけないのに、申告をしないでいると、税務署から決定の通知があり、この場合、徴収額に対して無申告加算税が課せられます。 また、決定前ではあるが申告が期限後である場合は、その申告が決定のあることを予知してなされたものでなければ加算税が課せられます。遺言
遺言とは、自分の財産をどのような形で誰に相続させるかを書き残すことです。 遺言をしておけば- 自分の意志に沿った財産分与ができる。
- 面倒を良く見てくれた人に財産を多くあげたい。
- 相続人とならない親族以外の人に財産をあげたい。
- 相続時の紛争を未然に防ぐことができる。
- 虐待や非行を行うものを相続人から排除したい。
相続・遺言の各種手続き
遺産相続・遺言であなたがお困りのことは何ですか? 相続のご相談は麿法務事務所へお任せ下さい。 亡くなった方の遺産を家族に引き継ぐ相続。 遺産の規模や家族構成によっては手続きが煩雑になるため、司法書士の力が必要になります。相続前・生前にできる事
~ご自身の財産の相続方法や相続税の対策を相談したい方へ~
相続発生によるトラブルが起きないよう事前に色々な対策をすることが出来ます。 何からすれば良いかまずは麿法務事務所にご相談ください。ご相談
推定相続人が知りたい、遺言書やエンディングノートを作りたい等生前に出来る手続きについてアドバイスさせていただきます。相続人の調査
相続人(法定相続人)に誰がいるのか調査を行います。 戸籍の収集や読み取り方は簡単ではありません。 当事務所では戸籍の収集から相続人関係図の作成を一括でお受けすることができます。 県外の戸籍でも収集できます。税金対策
税金の対策としては納税資金の確保と節税対策があります。 節税の方法には財産評価を下げる方法と生前贈与の2つが有効です。遺言書の作成
相続トラブルを防ぐための対策として遺言書の作成をお勧めします。 遺言書は決められた内容で作成する必要があります。 作成方法を間違えるとせっかく作った遺言書が無効になります。 失敗しないためにもまずは麿法務事務所にお気軽にご相談ください。相続発生時にしなければならないこと
~親などから財産を相続するようになった方へ~
相続発生後はたくさんの手続きがありそれぞれの期限が決められています。 相続人の方々が早く日常生活に戻れるよう麿法務事務所が手続きのアドバイスをいたします。7日以内の手続き
- 死亡届・埋火葬許可証交付申請
2週間以内の手続き
- 世帯主変更届
- 年金受給権者死亡届
- 加給年金額対象者不該当届
- 介護保険受給者証返却
- 老人医療受給者証返却
3ヶ月以内の手続き
- 相続放棄・限定承認の申述
- ※事前に遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続・財産の調査、概算把握が必要となります。
4ヶ月以内の手続き
- 所得税の準確定申告(その年の1月1日から死亡日までの所得税)
- 遺産分割協議
10ヶ月以内の手続き
- 相続の申告・納付
- ※相続財産の評価、相続税申告書の作成をする必要があります。
その他の手続き
- 遺言書検認の申立て
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- 相続税の還付手続
- 遺留分減殺請求(1年以内)
- 葬祭費の支給申請(2年以内)
- 埋葬費の支給申請(2年以内)
- 生命保険金の受取(原則3年以内)
麿法務事務所では、複雑な各種手続きを提携している関連会社とのネットワークであなたをサポートいたします。
さまざまな窓口にそれぞれ問い合わせするのが面倒だったり、どこに問い合わせていいか分からないという悩みをひとつの窓口ですべて対応することができます。
「相続問題で困った」という場合はまずは麿法務事務所にお気軽にご相談下さい。
- ご相談
- 相続に関するご相談は司法書士が親身になって対応いたします。 相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談下さい。
- 財産評価
- 資産の評価と言っても不動産や株式、保険など評価方法はそれぞれ異なります。
- 遺産分割協議書作成
- 相続人調査、財産調査、節税対策まで含めたご相談を承ります。
- 相続財産の名義変更
- 相続が発生した場合には不動産や車など財産の所有者の名義変更を行う必要があります。
- 遺言書作成
- 相続トラブルを防ぐための対策として遺言書の作成をお勧めします。
遺言・相続のQ&A
相続とは何ですか?
相続とは亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など、被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
自分にもしものことがあった時、誰が相続人になるんでしょうか?
亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となり、それ以外の人は、以下の順位で相続人となる事ができます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
<第1順位>被相続人の子供。既に死亡している時はその直系卑属(子や孫など)
<第2順位>被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
<第3順位>被相続人の兄弟姉妹
<第1順位>被相続人の子供。既に死亡している時はその直系卑属(子や孫など)
<第2順位>被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
<第3順位>被相続人の兄弟姉妹
相続の対象になる財産とはどのようなものですか?
相続の対象となる財産には、プラスの財産である現金や預貯金、土地や建物等の不動産、車や貴金属等の動産、株式や投資信託等の有価証券、借家権・借地権等の権利があります。また、借金や買掛金、医療費や水道光熱費などの未払経費、保証義務等、のマイナスの財産も、相続の対象となります。
>遺言を遺したいんですが、どんな方法があるのでしょうか?
遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。なかでも公証人が関与する「公正証書遺言」は、無効になりにくく、紛失や隠ぺいなどのリスクもない、確実性が高い形式として広く利用されています。
どんなタイミングでご依頼したらいいですか。
お客様が少しでも疑問をお持ちであればご連絡ください。無料相談を実施しております。相談したからといって必ず依頼しなきゃいけないということはありませんので、お話だけでもお聞かせください。